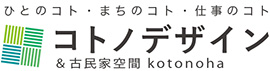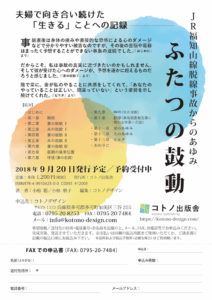お知らせ
8.172018
「ふたつの鼓動(コトノ出版舎)」の予約受付を開始しました
JR福知山線脱線事故からのあゆみ〜ふたつの鼓動
2018年9月20日発行予定
価格:¥1,296(本体:¥1,200)+送料
サイズ:A5判/ページ数:160p/高さ:148mm
ISBN:978-4-9910423-0-0 C0095
著者:小椋 聡/小椋 朋子
表紙デザイン/装丁:コトノデザイン
発行所:コトノ出版舎
〒679-1333 兵庫県多可郡多可町加美区三谷255
電話:0795-20-8253
FAX:0795-20-7484
【目次】
- はじめに
- 第一章 微熱
- 第二章 妻の鼓動 Ⅰ
- 第三章 夫の鼓動 Ⅰ
- 第四章 妻の鼓動 Ⅱ
- 第五章 夫の鼓動 Ⅱ
- 第六章 妻の鼓動 Ⅲ
- 第七章 最期の乗車位置
- 第八章 呼吸(妻の変調)
- 第九章 呻吟(夫の決断)
- 第十章 動悸(事故調査報告書に関わる作業〜示談)
- 第十一章 妻のあゆみ
- 第十二章 夫のあゆみ
- 第十三章 ピエタ
- おわりに
ご予約はこちらのコンタクトフォームに下記の必要事項を記載の上、お申込みください。完成次第、発送させていただきます。
お支払いは同梱の振込用紙をご使用いただくか、請求書に記載の振込口座にお振込み下さい。※送料および振込手数料(必要な場合)はご負担願います。
- 題名に「ふたつの鼓動予約について」とご記入ください。
- 希望冊数
- お名前(ふりがな)
- 送付先の住所
- 電話番号/メールアドレス
最近のお知らせ
-
2021/11/18
-
2019/5/31
-
2018/10/14
-
2018/9/25
-
2018/9/25
-
2018/9/20